「物価高で、もういっぱいいっぱいで…。このままだと、うちの子、大学に行かせてあげられないかもしれない」
先日、職場の同僚がご両親に教育費の援助をお願いしながら、そう言って頭を抱えていました。
マイホームも購入済みで順風満帆だった彼女が、今、こんなにも追い詰められている。これは決して他人事ではありません。
昨今の住宅価格の高騰もあり「早くしないと」という焦りから、つい「銀行が貸してくれる額」を上限に、目一杯のローンを組んでしまいがちです。
しかし、その計画に、10数年後に今の数倍にも膨れ上がる「子どもの教育費」は、本当に含まれているでしょうか?

家のせいで将来この子の『やりたい』を諦めさせることになったらどうしよう…

多くの人がやってしまう「今の家賃との比較」や「銀行が貸してくれる額」からの予算決めでは、子どもの教育費がピークを迎える頃に家計が苦しくなる危険が潜んでいます。
この記事では、そんな未来の不安を解消するために、筆者が実践してきた10数年後の未来から考える「逆算式」の予算策定術を具体的に解説します。
自分たちが無理なく返せる住宅ローン額や、筆者自身の経験に基づいたリアルな教育費についても紹介していくので、後悔しないための参考材料にしてください。
- 高校から大学卒業までにかかるリアルな教育費の総額
- 住宅ローン計画の「3つの落とし穴」
- 未来の教育費から考える安全な住宅予算の決め方
- 年収や家族構成別の具体的な住宅ローンシミュレーション
家計を襲う「二つの山」とは?教育費のリアルな総額

まずは、今後の教育費がどれくらいかかるのか、総額を把握しておくことが大切です。子どもが大学を卒業するまでに、一体いくらかかるのでしょうか?

実は、住宅ローンの返済期間中に、家計を直撃する大きな支出の山は2つあります。
第一の山(中ボス)|学習塾費+大学受験費用
大学進学がゴールだと思いがちですが、その手前には「受験」という大きな山が待ち構えています。これは、子育て世代の家計における「中ボス」と言えるでしょう。
受験は複数の大学を受験することが多く、また遠方の場合には交通費・宿泊費も必要となります。
この「第一の山」だけで、合計90万~140万円程度が大学の学費とは別に発生する可能性があるのです。
第二の山(ラスボス)|大学4年間の学費
そして、いよいよ家計の「ラスボス」、大学の学費です。
令和3年度教育費負担の実態調査によると、入学費用と4年間の在学費用を合わせた金額は、進路によってこれだけ大きく変わります。
- 国公立大学:約481万円(入学費用67.2万円+在学費用414万円)
- 私立大学(文系):約690万円(入学費用81.8万円+在学費用608万円)
- 私立大学(理系):約822万円(入学費用88.8万円+在学費用732.8万円)
さらに、忘れてはならないのが「見えない費用」です。もし子どもが一人暮らしをすることになれば、家賃や生活費の仕送りが必要になります。
仮に月8万円仕送りすると、4年間で約384万円。学費とは別に、もう一つ大学に通わせるくらいの費用がかかる可能性があるのです。

筆者が学生の頃は片道2時間半かけて電車通学していました。
学生定期券でも3カ月で10万円以上かかったので、苦しい出費です。
我が家の「ゴール金額」を設定しよう
ここまで見てきたように、高校から大学卒業までの教育費はまさに桁違いです。
「第一の山」である受験費用など(約140万円)と、「第二の山」である大学費用を合わせると、国公立大学でも約630万円、私立大学を視野に入れるなら800万~1,000万円という莫大な金額になります。(仕送りが必要な場合はプラス380万円程度必要。)
まずは、「我が家は国公立を目指すから700万円を目標にしよう」「いや、私立の可能性も考えて900万円は用意したい」というように、具体的な目標金額を夫婦で共有することから始めましょう。これが、無理のない住宅ローン「逆算」のスタート地点となります。
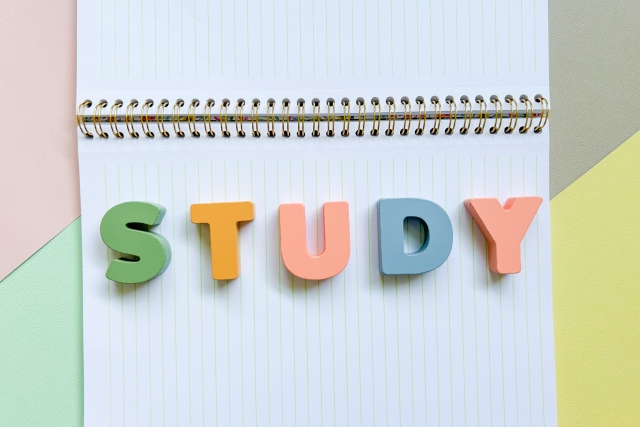
なぜ失敗する?住宅ローン計画の「3つの落とし穴」

未来の教育費という「ゴール」が見えたところで、次は多くの人がなぜ住宅ローンで失敗してしまうのか、その典型的なパターンを見ていきましょう。
これを先に知っておくことで、あなたの家づくりが同じ轍を踏むのを防ぐことができます。
落とし穴①「借りられる額」=「返せる額」という勘違い
住宅展示場や不動産会社の担当者に相談すると、「お客様の年収ですと、〇〇万円までお借り入れ可能ですよ」と言われることがあります。
しかし、この「借りられる額」を予算の上限にしてしまうのは致命的リスクです。
銀行のローン審査は、あくまで「現在の年収や勤務先を基に、返済が滞らないか」を見ているにすぎません。あなたの10年後、15年後の家計、そして子どもの教育費がいくらかかるかなんて、全く考慮してくれないのです。

「銀行が貸してくれるから大丈夫」ではなく、「自分たちが、将来にわたって無理なく返せるのはいくらか」という視点が何よりも重要です。
落とし穴②今の家賃との単純比較
「今の家賃が月10万円だから、同じくらいの返済額なら大丈夫だろう」と考えるのも、よくある落とし穴。
なぜなら、マイホームを持つと、ローン返済以外にも新たなお金がかかり続けるからです。
主な必要経費は以下の3つ。

筆者宅では、14年目に外壁・防水・防蟻等の修繕に約150万円かかりました。
修繕を怠ると家の寿命を縮めてしまうので、覚悟して準備しましょう。
これらの「見えないコスト」を考慮せずに家賃とローン返済額を比較すると、実際の家計は思った以上に圧迫されてしまいます。
落とし穴③「繰り上げ返済すればOK」という楽観論

「今は少し背伸びしたローンを組んでも、共働きで頑張って繰り上げ返済すれば、総支払額も減るし大丈夫」という考え方も危険をはらんでいます。
もちろん、繰り上げ返済は利息を減らす有効な手段です。
しかし、教育費がピークを迎える時期に、手元の現金を減らしすぎるのは得策ではありません。
大学の受験費用や入学金は、待ったなしで現金が必要になります。その時に「繰り上げ返済しすぎて、手元にお金がない…」という事態に陥っては本末転倒です。
住宅ローンの返済と、教育費のための貯蓄は、常にバランスを考えながら進める必要があります。
【3ステップ】教育費から考える「逆算式」住宅ローン予算の決め方

未来の教育費の大きさと、多くの人が陥る失敗パターンが見えてきました。
では、どうすれば「住宅ローンと教育費で生活苦」という事態を避け、安心して家づくりを進められるのでしょうか。
ここからは、将来の教育費から考える「逆算式」での予算算出方法を解説します。
「逆算式」とは?
多くの人が「今の年収は〇〇円だから、住宅ローンは△△円まで借りられる」と現在から未来を考えます。
それに対し「逆算式」は、「18年後に教育費が〇〇円必要だから、毎月××円は貯金する。だから、住宅ローンに回せるのは△△円まで」と、未来のゴールから現在を考える方法です。

次の3つのステップに沿って計算すれば、あなたの家族にとって本当に安全な予算が分かります。電卓やスマートフォンのメモ機能を用意して、一緒に計算してみましょう。
STEP1『聖域』としての教育費積立額を決める
まず、将来絶対に必要になる教育費を、毎月の家計から「聖域」として確保します。
- 教育費の目標総額を決める
第1章を参考に、我が家の目標額を決めましょう。
(例:私立も視野に入れ、900万円) - 現在の貯蓄額を引く
今ある貯蓄のうち、教育費用として確保できている金額を引きます。
(例:900万円 – 100万円 = 800万円) - 残り月数で割る
②で出た金額を、子どもが18歳になるまでの残り月数で割ります。
例えば、子どもが3歳の場合、残り15年 = 180ヶ月です。
【計算式】
(目標総額 – 現在の教育費貯蓄) ÷ 残り月数 = 毎月の積立額
【計算例】
(900万円 – 100万円) ÷ 180ヶ月 = 44,444円
この月々約4.5万円が、何があっても手を付けてはいけない「聖域」となります。毎月、給料が入ったら先取りで貯蓄に回しましょう。
つい使ってしまいそう…という方は、学資保険やNISAで国債など低リスク(とは言え元本割れのリスクはあります)のものに投資するという手もあります。

筆者はNISAと学資保険を組み合わせ、強制的に毎月口座引き落としされる仕組みにしています。まずはご夫婦で自分たちに合った方法を話し合ってみましょう!
STEP2「本当に返せる」毎月の返済上限額を出す
次に、毎月の手取り収入から、ローン返済にいくらまでなら回せるのかを計算します。
【計算式】
手取り月収 – (①生活費 + ②毎月の教育費積立額 + ③その他の貯蓄) = ローン返済上限額
- 生活費
今の家計簿を見て、食費、光熱費、通信費、保険料など、毎月必ず出ていくお金を合計します。 - 毎月の教育費積立額
STEP1で算出した「聖域」の金額です。 - その他の貯蓄
老後資金や車の買い替え費用など、教育費以外の貯蓄です。無理のない範囲で、月1万円でも確保しましょう。
例えば、手取り月収が40万円の家庭で、生活費が25万円、その他の貯蓄が1万円だとすると…
【計算例】
40万円(月収) – (25万円(生活費) + 4.5万円(教育費) + 1万円(予備費)) = 9.5万円
この9.5万円/月が、この家庭が住宅ローン返済に充てられる「本当の上限額」です。
STEP3「借りられる総額」と「物件価格の上限」を割り出す
最後に、STEP2で算出した月々の返済額から、購入できる物件価格の上限を導き出します。
- 借入可能額をシミュレーションする
STEP2で出た「ローン返済上限額」を、インターネットの住宅ローンシミュレーターに入力してみましょう。
【シミュレーション例】
月々9.5万円の返済 → 借入可能額は約3,100万円(条件例:金利1.5%固定、返済期間35年)
▶参考:ローン借入可能額 – 高精度計算サイト - 物件価格の上限を計算する
借入可能額に、自己資金(頭金)を足し、そこから物件価格の約7%といわれる「諸費用(登記費用や手数料など)」を引きます。
【計算式】
借入可能額 + 自己資金 – 諸費用 = 物件価格の上限(購入可能な金額)
【計算例】
3,170万円 + 自己資金500万円 – 諸費用250万円 = 約3,430万円
この3,430万円が、この家族にとっての「教育費を確保しながら無理なく購入できる物件価格の上限」となります。
年収・家族構成別住宅ローンシミュレーション


計算方法は分かったけど、うちの場合はどうなるのかな?

ここでは、具体的なモデルケースを使って、第3章のステップを一緒に見ていきましょう。
Case1 世帯年収550万円・子ども1人(2歳)の場合|約4,180万円
- 家族構成:夫(30歳)、妻(30歳)、子ども(2歳)
- 世帯年収:550万円(手取り月収 約35万円)
- 現在の貯蓄:400万円(うち教育費として100万円、自己資金として300万円)
- 現在の家賃:8万円
STEP1:教育費積立額を決める
- 目標:国公立大学も視野に入れつつ、私立文系レベルの700万円を目指す。
- 計算:(700万円 – 100万円) ÷ 192ヶ月(残り16年) = 月々31,250円
STEP2:ローン返済上限額を出す
- 生活費:家賃を除き、18万円と設定。
- その他の貯蓄:1万円
- 計算:35万円 – (18万円 + 31,250円 + 1万円) = 約128,000円
STEP3:物件価格の上限を割り出す
- 借入可能額:月々12.8万円の返済(金利1.5%、35年)→ 約4,180万円
- 諸費用:物件価格の7%と仮定。
- 計算:(4,180万円 + 自己資金300万円)÷ 1.07 = 約4,180万円
この家族の場合、安全な物件価格の上限は約4,180万円と算出できます。
Case2 世帯年収700万円・子ども2人(4歳、1歳)の場合|約3,630万円
- 家族構成:夫(35歳)、妻(33歳)、子ども2人(4歳、1歳)
- 世帯年収:700万円(手取り月収 約45万円)
- 現在の貯蓄:800万円(うち教育費として200万円、自己資金として600万円)
- 現在の家賃:11万円
STEP1:教育費積立額を決める
- 目標:子ども2人分。私立も視野に入れ、900万円 × 2人 = 1,800万円を目指す。
- 計算:(1,800万円 – 200万円) ÷ 204ヶ月(平均残り17年) = 月々約78,400円
STEP2:ローン返済上限額を出す
- 生活費:家賃を除き、25万円と設定。
- その他の貯蓄:2万円
- 計算:45万円 – (25万円 + 78,400円 + 2万円) = 約101,000円
STEP3:物件価格の上限を割り出す
- 借入可能額:月々10.1万円の返済(金利1.5%、35年)→ 約3,290万円
- 諸費用:物件価格の7%と仮定。
- 計算:(3,290万円 + 自己資金600万円)÷ 1.07 = 約3,630万円
この家族の場合、世帯年収は高くても子どもが2人いるため、安全な物件価格の上限は約3,630万円となりました。
年収だけで判断すると、もっと高い物件を買ってしまい、将来の教育費で苦しむ可能性があったかもしれません。
まとめ|あなたの計画が、家族の未来を守る最大の武器になる
ここまで、教育費の現実と、それに基づいた安全な住宅予算の算出方法について解説してきました。
住宅予算は「借りられる額」からではなく、「守りたい未来(=子どもの教育)」から逆算して決める。
この考え方こそが、10年後、20年後に「この家を買って、本当によかった」と心から思うための、何より大切な羅針盤になります。
なぜ、私がここまで計画の重要性を訴えるのか。 実は、私自身の親が予期せぬ多額の借金を抱えたことで、私の学生生活は一変したからです。
片道2時間半かけて大学に通い、月100時間のアルバイトに明け暮れる日々。やりたかった研究も、楽しみにしていたサークル活動も、すべて諦めざるを得ませんでした。
ほんの少しの想定外の出来事が、子どもの未来の選択肢をいとも簡単に奪ってしまう現実を、私は身をもって知っています。
家を買うことは、ゴールではありません。その家で、家族が笑顔で、豊かに暮らし続けることが本当のゴールです。

この記事を閉じたら、ぜひご夫婦で「我が家の教育費のゴールはいくらにしようか」「そのために、今から何ができるか」を話し合ってみてください。
その一歩が、10数年後の家族の笑顔を守る、最も確実な投資になるはずです。
ここまで資金計画についてお話してきましたが、そもそも教育費の負担そのものを少しでも軽くできたら、家計はもっと楽になりますよね。
特に、塾・予備校代は、家計への負担が大きい項目のひとつ。
そこで、選択肢の一つとしておすすめしたいのが、我が家も実践している質の高い通信教育の活用です。
中でも「Z会」は、難関大学への高い合格実績がありながら、通塾に比べて費用を大きく抑えることができます。
自宅で質の高い学習を進められれば、高額な塾代を節約し、その分を住宅ローンや大学の学費に充てることも可能です。
教育サービスも賢く選択して、マイホームの夢と子どもの未来、どちらも諦めない選択をしていきましょう。
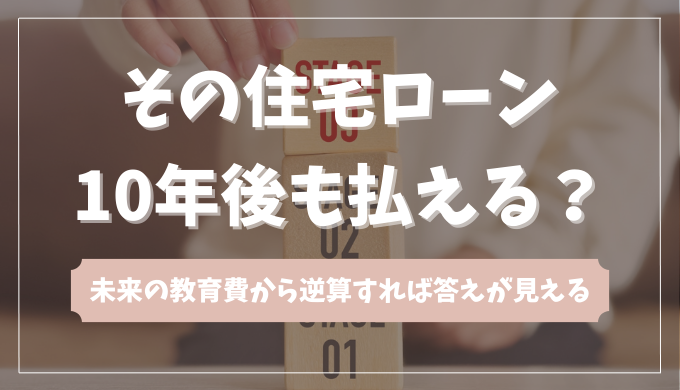

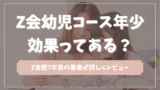
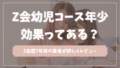
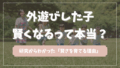
コメント