「小さい頃にたくさん外で遊んだ子は、賢くなる」
そんな話を聞いたことはありませんか?

でもそれって実際どうなの?遊んでばかりで勉強ができなくなるんじゃない?

実は「外遊びをたくさんした子どもほど賢く育つ」というのは、ただのイメージではなく複数の研究で裏付けられている事実なんです。
幼児期に体をたくさん動かした子ほど、
小学校で「勉強が好き」「集中力が高い」「友達が多い」と答える傾向がある
そんなデータが、大学の調査で明らかになっています。
今回は、なぜ外遊びが賢い子を育てるのか、科学的な理由と家庭での活かし方を解説します。
出典
- 幼児期の外遊びが学力・集中力に与える影響
- 「自発的な遊び」が思考力・自己効力感を伸ばす理由
- 外遊びを通して考える子を育てるコツ
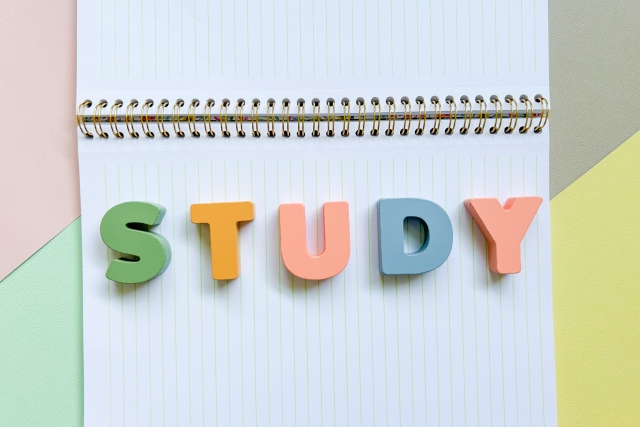
外遊びをたくさんした子は「勉強が好きになりやすい」

「外で遊んでばかりじゃ勉強が遅れそう…」
と不安になりますが、たくさん体を動かす遊びをした子の方が賢くなるという研究結果もあります。
ここでは、具体的にどのような効果があるのか、研究内容を元に解説していきます。
幼児期の外遊びが「学ぶ意欲」を育てる
外で元気に遊ぶことは、単なる体力づくりではありません。
研究によると、幼児期に体をたくさん動かした子どもほど、小学校で「勉強が楽しい」と感じる傾向があることが分かっています。
女子栄養大学の調査では、幼児期に「体を動かすことが好き」と答えた子どもは小学校で
と回答する子が多いという結果が出ています。
つまり、幼児期に遊びの中で感じた「楽しい!」という感情が、そのまま学びへの好奇心につながるのです。

じゃあ外遊びに積極的な幼稚園とかに入れたほうが良いってこと?

ところが、そういうわけでもないようです。
「園が運動中心だったか」よりも「自発的に遊んだか」が重要
同じ研究では、
「園がどの程度運動活動を重視していたか」と「小学生になってからの体力・学力」とのあいだには、明確な相関は見られませんでした。

つまり、環境よりも本人の意欲が大事だということ。
公園が広いかどうか、保育園に運動プログラムがあるかどうかより、子ども自身が「やってみたい!」「もっとできるようになりたい!」と感じられる体験こそが、のちの集中力や探究心の土台になります。
外遊びがもたらす「自己効力感」とは?
外遊びでは、失敗と成功の体験を何度も繰り返します。
- ジャングルジムに登れなかったけど、次の日に登れた
- 走るのが遅かったけど、少しずつ速くなった
- 泥だらけになっても最後まで頑張った
こうした小さな成功体験が、「自分はできる」という自己効力感を育てます。
「自己効力感」とは
自分がある状況においてやるべき行動を「うまくできる」と信じられること
のこと。カナダの心理学者アルバート・バンデューラが提唱した概念です。
この自己効力感は、心理学的にも学ぶ意欲と強く関連していることが分かっています。
外遊びは「頑張ればできる」という感覚を通して、勉強にも前向きに取り組める子を育てるのです。
外遊びが「考える脳」を育てる

外遊びで走ったり登ったりしているとき、子どもの脳では考える力を司る部分がフル回転しています。体を動かすことが、思考力のトレーニングになっているのです。
幼児期は神経系の発達が最も活発な時期
幼児期(3〜6歳)は、脳と神経系が急速に発達するゴールデンタイムと言われます。
特にこの時期は体の動きに関わる神経ネットワーク(運動神経・感覚神経)が爆発的に伸びる時期であり、「走る・跳ぶ・回る」といった多様な動きが脳内のシナプス形成を促します。

この時期に体を使った遊びが少ないと、神経回路の発達チャンスを逃してしまいまうんです。
研究でも、運動経験が豊富な子どもほど動作だけでなく思考・判断・集中に関わる前頭前野の活動が活発であることが報告されています。
体を動かすことで前頭前野が鍛えられる
外遊び中の「走る・登る・バランスを取る」などの動きは、脳の中でも特に前頭前野を刺激します。
前頭前野は、集中力や記憶、論理的思考、創造力をつかさどる部分。 ここを活性化させるのが、外遊びのような全身を使う経験なんですね。
たとえば、木登りをする子どもは「どこに足をかけるか」「どうすれば落ちないか」と瞬時に判断しながら動いています。その瞬間ごとに、脳は試行錯誤を繰り返し、考えながら動く習慣を自然に身につけているのです。
机の上の勉強では、思考は言語や記号に限定されがちですが、外遊びでは体全体を通して「考える・選ぶ・判断する」プロセスを何度も経験します。

その積み重ねが、思考力・集中力・問題解決力につながるってことか。

外遊びの力、侮れませんね。
国立教育政策研究所や発達心理学の分野でも、身体を動かす活動が記憶や理解の定着を助けるという報告があります。
体を動かすと脳内の血流と酸素供給が増え、記憶や学習を担う海馬の働きが活発になることが確認されています。外遊びのあとに勉強をすると集中力が高まり、吸収が良くなるというデータも。
外遊びで「語彙力」と「社会性」が育つ

走る・登るだけが外遊びではありません。
友だちとのやり取りやルール作りの中で、言葉・協調性・思考力もぐんぐん伸びていきます。
自由遊びが多い子ほど語彙力が高い傾向
外遊びの効果は、体や脳だけにとどまりません。
言葉の力──つまり語彙力やコミュニケーション力にも、はっきりと影響が見られます。
国内外の幼児教育研究では、自由遊びの時間が長い園ほど、子どもの語彙得点が高いという結果が報告されています。
たとえば、一斉指導で文字を教える園よりも、自由遊びを重視する園の子どものほうが「自分の考えを言葉で伝える力」が豊かだといわれています。
これは、遊びの中で自然と「言葉を使う場面」が多いから。
- 「鬼ごっこする人、こっち来て!」
- 「次わたしがやっていい?」
- 「じゃあここをゴールにしよう!」
こうしたやり取りの積み重ねが、子どもたちの語彙をどんどん増やしていくのです。

座学よりも実践が大事、ということですね。
「強制型」より「共有型」しつけが賢さを伸ばす
さらに興味深いのは、親の関わり方によって語彙力や思考力に差が出るという研究結果。
「早くしなさい」「ダメ」「やめなさい」といった強制型のしつけよりも、「どうしたい?」「一緒にやってみよう」と共有型のしつけをする家庭の子どものほうが、読み書き能力・語彙の得点が高い傾向があると報告されています。
外遊びは「共有型コミュニケーション」が生まれやすい場。一緒にボールを追いかけたり、落ち葉を拾って遊んだりする中で、親子が同じ体験を言葉にしながら共有できます。
「すごいね、あんな高いところまで登れたね!」
「この葉っぱ、さっきのと形が違うね」
こうした言葉のキャッチボールが、子どもの語彙力と思考力を同時に伸ばしていくのです。

付き合う親も大変だけど、できる範囲でやっていきたいな。
遊びの中で身につく言葉・思考・協調性
遊びは、いわば小さな社会の練習場。順番を守る、ルールを決める、相手の気持ちを考える。
どれも、机の上では学べない社会力です。
たとえば、ケンカや意見の食い違いも外遊びの中ではよく起こります。これも貴重な学び。
「どうすればうまくいくか?」を考える過程で、論理的思考・感情のコントロール・共感力が少しずつ育っていきます。
言葉を使って相手とやり取りするうちに、「伝える力」と「聞く力」が磨かれ、結果として語彙も豊かになり、後の読解力や作文力にもつながります。

最近は習いごとなどで外遊びの時間が減っているとも言われますが、
大切なのは量ではなく質。
1日30分でも、自分で考えて遊ぶ時間があれば十分に力は育ちます。
賢い子に育つ「外遊び」のコツ

「具体的に、どれくらい遊べばいいの?危険もあるし不安…」
と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
ここからは遊ぶ時間やコツについて見ていきましょう。
1日最低60分を目安に外遊びをしよう
日本スポーツ協会(JSPO)が発行した『アクティブチャイルド60min. ― 子どもの身体活動ガイドライン ―』では、子どもに必要な身体活動量は1日合計60分以上と定められています。
この「60分」は運動だけでなく、公園で遊ぶ・散歩する・自転車に乗るなど、日常の中で体を動かす時間も含めた総計です。
太陽の光を浴びることで体内時計が整い、集中力を高める「セロトニン」も活発に分泌されます。また、走る・登るなどの全身運動は脳の血流を促し、前頭前野や海馬を刺激します。
短時間でも「毎日少しでも体を動かす習慣」を続けることが、子どもの脳と心を育てます。
「危ない」より「やってみよう」を増やす
外遊びの本質は「危険を避ける」ことではなく、小さな挑戦の中で学ぶことにあります。
少し高いところに登る、初めての遊具に挑戦する、友達と意見を交わしてルールを作る。
こうした体験の積み重ねが、子どもの思考力・判断力・自己効力感を育てます。
もちろん安全の確保は必要ですが、危険をすべて取り除くよりも「どうすれば安全にできるか」を一緒に考える姿勢が大切。

なんか難しそう…それって具体的にどうすればいいの?
例えば滑り台を逆から登ろうとしたら
「上から人が来たらどうなるかな?」
「じゃあ、いないときにやってみようか?」
など、安全にできる条件を一緒に考えてあげましょう。
失敗を恐れずに試してみる経験こそ、勉強にも通じる「自分で考えて動く力」の源になります。

と言っても実際は、そううまくいかないことも多いですよね。
最初からうまくいかず当然と割り切るのも大事です。
親のストレスになるのも本末転倒ですしね。
「遊び」と「学び」を両立できる家庭学習法ってある?

習いごとほどガッツリじゃなくても、勉強の習慣もちょっとずつつけておきたいな。遊ぶ時間を確保しながらできる幼児教育ってある?

家庭のペースで無理なく続けるなら「Z会」の幼児コース・小学生コースがおすすめです。
筆者宅でも長女・次女ともに3歳から7年間続けています。
学習ペースが身につき遊ぶ時間もたっぷりとれたので、充実した幼児期を過ごせましたよ!
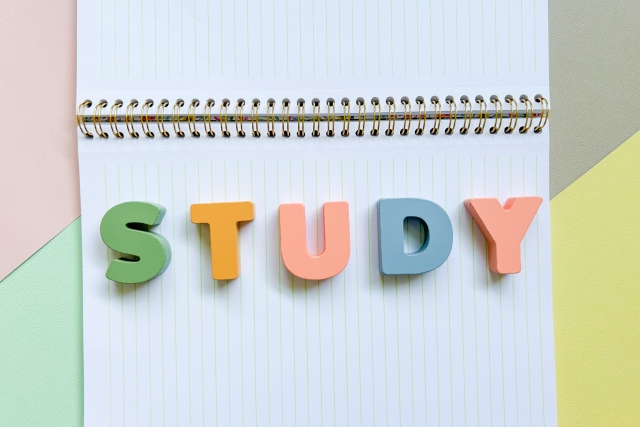
まとめ|外遊びを通して
外で思いきり遊ぶことは、単なる体力づくりではありません。
「楽しい!」という気持ちが学びへの好奇心を育て、失敗と成功のくり返しが自信(自己効力感)を生み、仲間とのやり取りが語彙力や社会性を育てます。
研究でも、幼児期に体を動かす経験が多い子ほど小学校で「勉強が好き」「集中できる」「友達が多い」と感じる傾向があることが分かっています。
「もっと習いごとをさせたほうが良い?」
「遊んでばかりでうちの子大丈夫?」
と悩むことも多い育児ですが、安心してたくさん外遊びをさせてあげましょう。
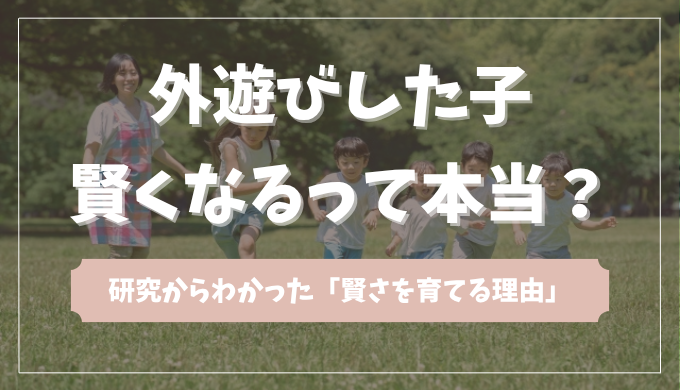

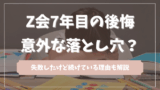
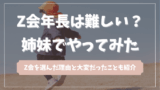
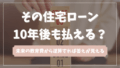
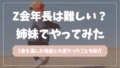
コメント